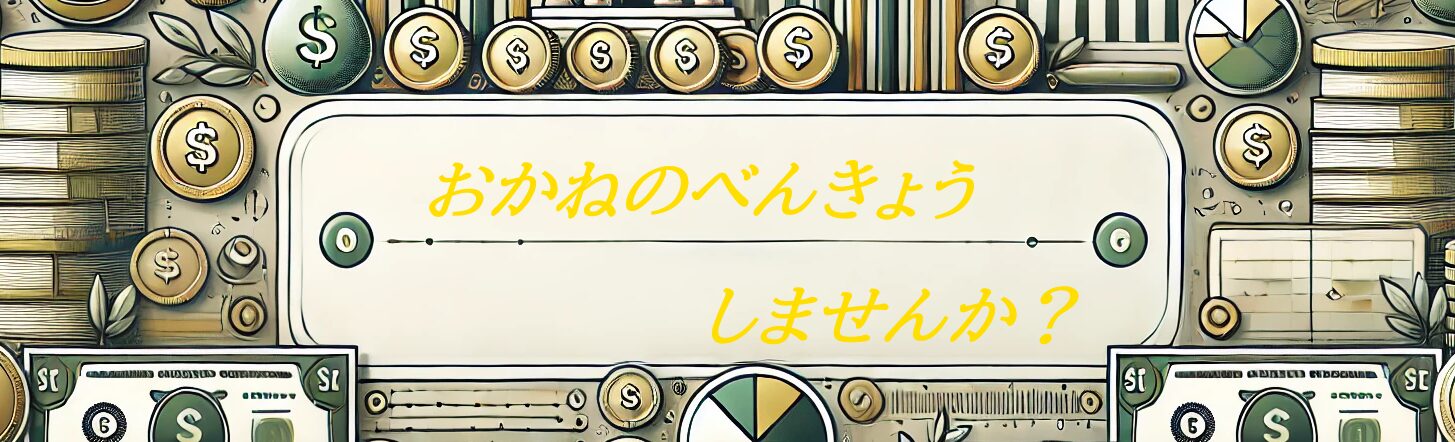初めて当サイトにいらしてくださった方は、まず、サイトのトップページにある「はじめに」を読んでいただけると幸いです。
また、筆者の来歴や保有資格は「筆者プロフィール」をご覧ください。皆さんに何か買わせたり、セミナーに勧誘する怪しい者ではありませんのでご安心を。
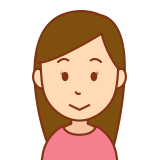
日本と海外で税制度に違いってあるの?
前回は、日本と海外の税制度の違いについて解説しました。前回の記事はコチラ
今日は「高い税金」と「安心できる生活」の関係について、海外の事例を交えてお話ししようと思います。「税金が多すぎる!」と文句を言いたくなるかもしれませんが、実はそのおかげで国民みんながしっかりと守られている、という意外な一面があるんです。今回は、北欧やヨーロッパの先進国を中心に、税金が社会保障にどのように活かされているのか、そしてそこから学べることは何かを考えてみましょう。

2024年に日本は最高税収を記録しました。なんと、78兆4400億円!でもまだ足りないんだってさ。ウケる。
北欧モデルの秘密
まずは北欧諸国。スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランドなど、税率は世界でもトップクラス。しかしその一方で、医療、教育、子育て支援、失業保険など、充実した社会保障制度が整備されています。たとえば、北欧の国々では、税金のおかげで病院の医療費がほぼ無料になっていたり、子供の保育園や学校の費用が実質無料で提供されたりするため、経済的な心配が少なく、家族みんなが安心して暮らせる環境が整っています。これにより、国民は「税金を払うストレス」よりも、「必要なときにしっかりサポートしてもらえる安心感」に価値を見出しているのです。
また、北欧の制度は「平等主義」を徹底している点も見逃せません。高所得者ほど多く税を負担し、その分低所得者にも手厚い福祉が行き渡る仕組みになっており、社会全体の格差を小さく保つ工夫が施されています。国民同士の信頼関係や、政府への信頼も厚く、結果として「みんなで助け合う社会」という理念が根付いているのだと思います。

負担は大きくても、恩恵がでかければ文句もないわな。
ヨーロッパ各国の事例
北欧以外のヨーロッパ諸国も、似たような成功例を見せています。ドイツは、高い税率とともに、充実した健康保険制度や年金制度、失業保険制度が整えられており、何かトラブルがあっても国民が一人ひとり孤立しない仕組みが構築されています。たとえば、ドイツでは急な病気や怪我に対しても、医療費の負担が軽減される仕組みがしっかりしており、経済的リスクを最小限に抑えられるのが大きな魅力です。
また、フランスも税金を通じた社会保障の代表格と言えるでしょう。高い社会保険料を負担する代わりに、病院や医療サービス、さらには公共交通機関や文化施設の利用など、多方面で国民に還元される仕組みがあります。フランスの人々は「税金が大変だ」と嘆くよりも、そのおかげで得られる豊かな生活環境を実感しているようです。
これらの国々では、税率が高いという事実は、むしろ「社会全体の安心感」や「将来への備え」として受け止められており、個々の負担感よりも全体のメリットが勝っていると考えられています。

必要な部分に使われているのが目に見えると安心できるし、不満も減るよね。
税金がもたらす安心感とその裏側
もちろん、「高い税率=損」と一蹴する意見もあるでしょう。自分の給料からかなりの額を天引きされるのは、確かに痛いですよね。でも、ここでひとつ考えてほしいのは、万が一の時に大きな医療費や失業という不測の事態に直面したとき、国全体で支え合う制度があれば、個人としてのリスクは大幅に下がるということです。個人で貯金しておいても、予測できない事故や病気、経済の浮き沈みを完全にカバーするのは難しいものです。税金という形で国民全体がリスクを共有することで、みんなが安心して生活できる環境が作られているのです。
また、こうした社会保障制度は、子育て世代にとっても大きなメリットがあります。保育園の費用補助や教育費の軽減、さらには長期休暇中の収入保障など、子育てにかかる経済的な負担が軽減されるため、安心して子供を育てることができる環境が整っています。結果として、出生率の向上や若い世代の生活の質の向上にも寄与していると言われています。
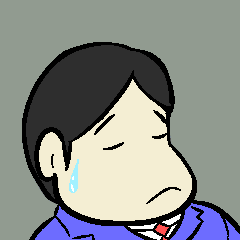
出生率自体は下がり続けてますけどね。少子高齢化の記事はコチラ
日本との比較と今後の展望
一方で、日本は必ずしも「高税率=充実した社会保障」というイメージが強くないかもしれません。確かに、医療保険や年金制度、介護保険などが整備されつつありますが、実際にはサービスの質や行き届き方にばらつきがあり、負担感と受給感のギャップを感じる人も多いのが現状です。北欧や西欧の例を見れば、もう少し税金の使い方や制度設計に工夫を凝らせば、日本ももっと「安心して暮らせる国」になれるのではないかという期待が湧いてきます。
ただ、制度改革というのは簡単なものではありません。国民の考え方や文化、歴史的背景が大きく影響するため、一概に「これが正解!」という答えは出にくい部分もあります。しかし、税金を単なる「取り立てるもの」ではなく、国民一人ひとりの未来への投資と捉え直す視点は、どの国でも重要な課題と言えるでしょう。
また、近年はグローバル化が進み、世界中の国々が互いに良い制度やアイデアを学び合う時代になっています。北欧の社会保障制度をはじめ、ヨーロッパ各国の取り組みは、他国が模倣し、改良するための貴重なヒントになっています。たとえば、働き方改革やワークライフバランスの実現に向けた政策は、単に高い税金があれば実現できるというわけではなく、国民全体が制度に対する信頼を持ち、将来に希望を抱ける環境づくりが必要不可欠です。
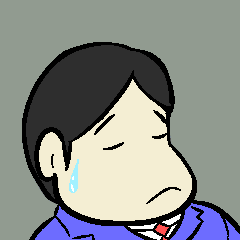
日本の制度も素晴らしく、快適に暮らせる国ではありますが、不透明感があるのは否めません。
まとめ
高い税率は一見、財布に厳しい印象を与えますが、実際にはその税金が充実した社会保障制度として国民に返ってくるという考え方もできます。北欧やヨーロッパ諸国の例は、税金を賢く使うことで、国民全体が安心して暮らせる社会を築いていることを示しています。もちろん、日本にも改善の余地はありますが、世界各国の先進的な取り組みから学ぶことは多いはずです。
自分自身のライフプランやリスクマネジメントを考えるとき、個人で全てを賄うのではなく、社会全体で支え合う仕組みのありがたみを実感できるのではないでしょうか。今後の政策議論や制度改革の参考として、こうした「高い税金とそのリターン」の関係に目を向けるのも、私たちの生活をより豊かにする一つのヒントかもしれません。
読んでいただいた皆さんも、ぜひ自国の制度や他国の取り組みについて、改めて考えてみてください。たとえ税金が高く感じても、その先にある安心と安全、そして共に支え合う社会の価値は、何物にも代えがたいものだと感じられるはずです。
この記事が、皆さんの新たな可能性の気付きの一助となれば幸いです。
今回の記事は以上です。知識という武器を身に着けて、今後も資産を増やしていきましょう!

次回も私と一緒にお金の勉強をしましょうね!
※本記事はあくまで一般的な情報提供を目的としており、最新の法改正や個別の事情に関しては、専門家への相談をおすすめします。税金の話題は常に変動しているため、最新情報のチェックもお忘れなく!